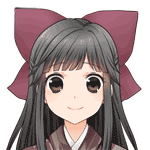はいっ!
たまこです。いつもありがとうございますっ♪
お正月を迎え、初詣、おせち料理やお雑煮、お年玉などたくさんのお正月行事や風習がありますよね。
そのお正月の風習の中に「お屠蘇(おとそ)を飲む」という風習があるのをご存知でしょうか。たまこは自分で調べてみるまで、お屠蘇のことを知らなかったのですが、古くから伝えられている伝統的なお正月行事です。
今回は、そのお屠蘇について詳しく調べてみましたので、ご紹介させて頂きますね^^。
[st_toc]
スポンサーリンク
お屠蘇(おとそ)とは、いったい何?飲む意味は?

By: midorisyu
お屠蘇とはお正月に飲む「薬酒」のことです。
お正月に飲むことから、一般的にはお神酒と同じ日本酒と思われがちですが、実は中国から伝わった伝統的な薬酒のひとつなんですっ。
「薬酒というのは、漢方薬を漬け込んだお酒のことで、漢方薬の薬効がお酒に溶け込んで薬として飲まれている特別なお酒です。」
お屠蘇という名前は、蘇と呼ばれる悪鬼を屠るという意味から名付けられました。
中国のお屠蘇の歴史をひも解くと、中国の六世紀ごろの古典書物(荊楚歳時記)にも次のように記載されています。
元旦長幼ことごとく衣冠を正し、順序に従って拝賀を行い、椒柏(ショウハク)の酒・桃の酒・屠蘇酒(トソシュ)・膠牙餳(コウガトウ)・五辛盤(ゴシンバン)・敷于散(フウサン)・却鬼丸(キャッキガン)などを飲みかつ食う」
この記述にある「屠蘇酒」が今のお屠蘇に当たります。
元旦になると邪気を払い不老長寿になれる薬酒として年少者から順番に飲んだということです。
六世紀から飲み続けられてきたとは、、、とても伝統的なお酒ですよね。
この屠蘇酒を中国ではお正月に飲む風習があり、日本にもその風習が伝わったとされています。
日本でのお屠蘇の歴史を見てみると、平安時代の初期に伝わり、最初は宮中で飲まれていましたが、江戸時代頃から一般庶民にも飲まれるようになったみたいですね。
お正月の元旦にお屠蘇を飲む意味には、1年の邪気や悪鬼を屠り、生気を蘇らせ、延命長寿が得られるという意味があります。
お屠蘇(おとそ)はどんな時にどんな場所で飲むの?
お屠蘇は、新年に邪気を払うために飲む縁起の良いお酒です。
伝統的な風習に習って、元旦に家族がみんな揃って新年の挨拶をした後、杯をまわして順番に飲みましょう!
お屠蘇(おとそ)を注ぐ屠蘇器ってどんなもの?
お屠蘇を飲むためには「屠蘇器(とそき)」と呼ばれる杯と銚子と台のセットを用意します。
こちらが屠蘇器です。伝統的な漆塗りの器です。綺麗ですよね。
朱色の杯が大・中・小と三種類重ねて置かれ、その右側にはお屠蘇を注ぐ銚子が備わっていて、それらを屠蘇台と呼ばれる台の上に並べたものです。
屠蘇器は、実際に使用するまでは床の間の脇床に置いておきます。そのとき、屠蘇器の正面が見えるように置きます。
朱色の杯は左側に重ねて置き、銚子は右側に置くようにするのが伝統的な並べ方です。
お屠蘇を頂く時の正式なお作法では、屠蘇器の朱色の杯3種に3献ずつ頂くものらしいですが、一般的には一番上の小さな杯を使って、下の2つの杯は使用しなくても良いとされています。
ちなみに屠蘇器が無い場合は、普通のおちょこやグラスで飲んでも大丈夫です!
お屠蘇(おとそ)を飲むときの作法や飲み方は?
お屠蘇を飲むときに重要なお作法は、飲む順番ですっ!
最年少者から東を向いて
お屠蘇を飲む時は、まず家長が年初の挨拶をして屠蘇を神に捧げた後、最年少者から東を向いて順番に飲むようにします。
なぜ、年少者から飲むのか?というと、息災を祝う意味が込められているのと、若い人の若さを次の年長者が飲み取るという願掛けの意味もあるようです。
ですから、なるべく若い人から年齢順に飲んで行くのが正しい飲み方と言えます。
若い人は年長者を敬い、一年を健康的に過ごせるように祈りながら飲むようにすると良いと思いますっ^^
お屠蘇の飲み方
祝い酒ですが、実際に飲むときは、三三九度のように分けて飲まずに普通に飲みます。
それでは、続いてお屠蘇の作り方をご紹介致しますねっ!
スポンサーリンク
お屠蘇の作り方と屠蘇散の中味
お屠蘇の作り方
お屠蘇を作るには、屠蘇散と呼ばれる漢方薬を三角形の絹の袋にいれ、日本酒やみりんに浸して作ります。
もともと中国では、大晦日に屠蘇散に使われる薬草を噛み砕いて朱色の袋にいれて、井戸の中に一晩吊るしてエキスを染み出させてから、元旦にそれを袋ごと酒に浸して飲むものでした。
現在は、薬草の種類も減り、井戸に一晩吊るして浸しておく手間が省かれているようです。
お屠蘇を作る際の手順
お屠蘇っぽい味わいのお屠蘇を飲みたい場合
- 日本酒300ml程度を屠蘇器の銚子に注ぎます。
- 屠蘇散の入った袋を浸します。
- 6〜8時間ほど浸けた後に、屠蘇散を取り出して完成です。
甘さとコクを楽しみながらお屠蘇を飲みたい場合
- 本みりん300ml程度を屠蘇器の銚子に注ぎます。
- 屠蘇散の入った袋を浸します。
- 6〜8時間ほど浸けた後に、屠蘇散を取り出して完成です。
☆すっきりした後味と甘さ、コクをバランスよく楽しみたい場合
- 日本酒150ml(端麗がオススメ)と本みりん150mlを屠蘇器の銚子に注ぎます。
- 屠蘇散の入った袋を浸します。
- 6〜8時間ほど浸けた後に、屠蘇散を取り出して完成です。
お屠蘇を作る時の注意点
- 市販の屠蘇散は、購入時に添付された説明書の指示の通りに使用してください。
- 屠蘇散の取り出し忘れに気をつけてください。長時間浸すと、苦みが出て来てしまいます。
- みりんには、必ず本みりんを使用して下さい。みりん風調味料は化学調味料や塩分、糖分などが入っていてアルコール分も1%未満のため美味しくありません。
屠蘇散の中味
屠蘇散の中味は5〜10種類の漢方薬を調合したものです。
Wikipediaで屠蘇の項目をみてみましょう。
屠蘇散の処方は『本草綱目』では赤朮・桂心・防風・抜契・大黄・鳥頭・赤小豆を挙げている。現在では山椒・細辛・防風・肉桂・乾薑・白朮・桔梗を用いるのが一般的である。人により、健胃の効能があり、初期の風邪にも効くという。時代、地域などによって処方は異なる。
By: 屠蘇 - Wikipedia
と書かれています。
また、書籍では、
大黄(だいおう)
蜀椒(しょくしょう)
桔梗(ききょう)
桂心(けいしん)
防風(ぼうふう)
白朮(ひゃくじゅつ)
虎杖(いたどり)
烏頭(うず)
By : 日本の「行事」と「食」のしきたり 新谷尚紀 著
以上が屠蘇散の原料とされています。
一般的には、これらの漢方のうち5〜7種類程度がブレンドされているものを使用する場合が多いようですね。
市販されているお屠蘇の原料には、こちらの漢方が使われていました。
山椒(さんしょう)
肉桂(にっけい)
白朮(ひゃくじゅつ)
防風(ぼうふう)
大黄(だいおう)
蜜柑(みかん)
皮(ひ)
屠蘇散はセットで売られています。屠蘇散を購入するなら
屠蘇散は袋にセットされた状態で薬局などで販売されています。
Amazonでも購入できますよ。
[amazonjs asin="B00G7G7X7Y" locale="JP" title="おくすり屋さんの屠蘇散(3包入り)"]
こちらを大晦日に日本酒やみりんに浸せば、元旦にはお屠蘇の完成です。
さらに、Amazonでは完成した薬酒としても売られていましたっ。
[amazonjs asin="B006ISJQVW" locale="JP" title="春鹿 屠蘇酒延寿 300ml"]
まとめ
今回の記事では、お正月のお屠蘇について詳しくご紹介させて頂きました。
年少者から東を向いて飲むというお屠蘇の風習の意味や、お屠蘇は作り方によって好みの味が作れる点など調べてみて勉強になりました。
ぜひ皆様もお屠蘇を飲む際や作る際に参考になさってくださいね!
今日もたまこの知恵袋を読んで頂き、ありがとうございましたっ!
お正月の鏡餅の飾り方もこちらのページで丁寧に解説しています。
鏡餅に飾る品のひとつひとつの意味も解説していますので、良かったらご覧になってくださいね!